日本の税金って“高い”?|北欧やアジアとくらべてわかる、支え合いの仕組み
「うちって、税金払ってるの?」 ある日、子どもにそう聞かれて、うまく答えられなかったことはありませんか? 自営業の家庭では確定申告をして税金を納める場面が目に見えやすいけれど、サラリーマン家庭では“給料から自動で引かれてる”ことすら、子どもにはわかりません。 この記事では、「税金って高すぎない?」「どこに使われてるの?」という親子の素朴な疑問から出発し、他の国々と比べながら“支え合い”のしくみとしての税金を一緒にひもときます。 消費税や所得税の見え方の違いだけでなく、「どこに納得できるか」「何がモヤモヤなのか」を考えるきっかけにしてみましょう。
「税金って高すぎない?」親もモヤモヤする“子どもの素朴な疑問”
「うちって税金払ってるの?」家庭によって“見え方”がちがう
子ども同士の会話で、「Aくんちは確定申告してるって言ってた」「うちはしてないけど、それって払ってないってこと?」といった疑問が出ることがあります。 家庭によって、税金が“見える”場面はまったく違うんです。 実際には、どの家庭も何らかのかたちで税金を負担していますが、その「納め方」「見え方」が違うことで、「うちは損してる?」「あっちはズルしてる?」という誤解にもつながります。
自営業と会社員では“払い方”も“感覚”も大違い
自営業の人は、年に1回の確定申告で税額を計算し、支払いをします。子どもも「領収書を集めてる親」を見て「大変そうだな」と感じるかもしれません。 一方で、会社員の場合は毎月の給料から「所得税」や「住民税」が自動的に引かれます。 そのため、“納めてる感”が薄くなりがちで、「いつの間にか取られてる」「知らないうちに減ってる」と感じる人も少なくありません。
経費や控除…「なんかズルくない?」という子どもの目線
「自営業はなんでも“経費”で落とせてズルい」「うちはまじめに取られてるだけじゃん」—— そんな気持ちを抱いたことがある親も、いるかもしれません。実際にはそれぞれにルールや制限があるものの、仕組みが見えづらいからこそ“ズルく見える”のです。 この“モヤモヤ”の正体は、「金額」ではなく「納得できないこと」。 まずはそこに向き合うことから、税金のしくみを見直していきましょう。
世界の税金、“払ってる感”と“返ってくる感”がちがう?
北欧の国は「税率高いけど、教育・育児・介護まで幅広くカバー」
たとえばフィンランドやスウェーデンなどの北欧諸国では、消費税が25%前後、所得税も高く設定されています。 でもそのかわり、大学までの教育費が無料だったり、出産・育児・介護に至るまで手厚い支援が受けられる国もあります。 「高いけれど、ちゃんと返ってくる」——だから国民の満足度が高いのです。 「納得できる税金かどうか」が重要なんですね。
アメリカは「税金少なめ、でも貧富の差がダイレクトに」
アメリカでは、所得税や消費税が比較的低く、自由競争や自己責任を重んじる社会です。 その反面、医療費や大学の学費がとても高く、「自分で備えなければ、何も保障されない」という厳しさもあります。 税金が少ない=負担が軽い、とは限らず、「いざというときの備え」もすべて自己責任という現実があります。
日本は“中くらい”…でも税金の“使われ方”が見えにくい?
日本の税率は、北欧よりは低く、アメリカよりはやや高め。ちょうど“中間”くらいの立ち位置です。 ただし、「何に使われているのか」が見えにくく、納得しづらいという声も多いのが現実です。 ちなみに、病院の窓口で「医療費3割負担」で済むのは「社会保険」のしくみ。 税金とは別の制度ですが、「公的に支え合っている」という点では共通しています。 気になったら、「ケガしても1,000円で済んだのはなんで?」の記事もおすすめです。
税金って“とられる”もの?それとも“出し合う仕組み”?
子どもたちの学校や図書館、誰のためにある?
ふだん当たり前に使っている公立の学校、図書館、公園や道路、消防や防災のしくみ—— これらの多くは「税金」によって支えられています。 「タダで使える」ように見えても、誰かが払った税金によって成り立っている。 それを子どもと一緒に意識するだけでも、“社会とのつながり”が変わってきます。
今“払ってる人”も、将来“助けられる人”になるかもしれない
税金は「今、払う人」が「今、困っている人」を助ける仕組みです。 でもそれは、“立場が変われば誰もが支えられる側になる”ということでもあります。 たとえば失業中の手当、災害時の支援、高齢者の介護や年金制度。 「自分とは関係ない」と思っていたことが、ある日、必要になるかもしれません。
社会保険とちがって、税金は「みんなの共有資源」に近い
医療費や年金のように、あとで“自分に返ってくる”前提の社会保険とは違って、税金は「返ってくる保証」があるわけではありません。 だからこそ、「どう使われるか」「納得できるか」がとても大切です。 税金は、“みんなで出し合い、社会を運営するためのお金”なんです。
「高いか安いか」だけでなく、「どう使われるか」「なぜ必要なのか」を、親子で一緒に考えてみる。 そんな対話が、これからのマネーリテラシーの第一歩になります。

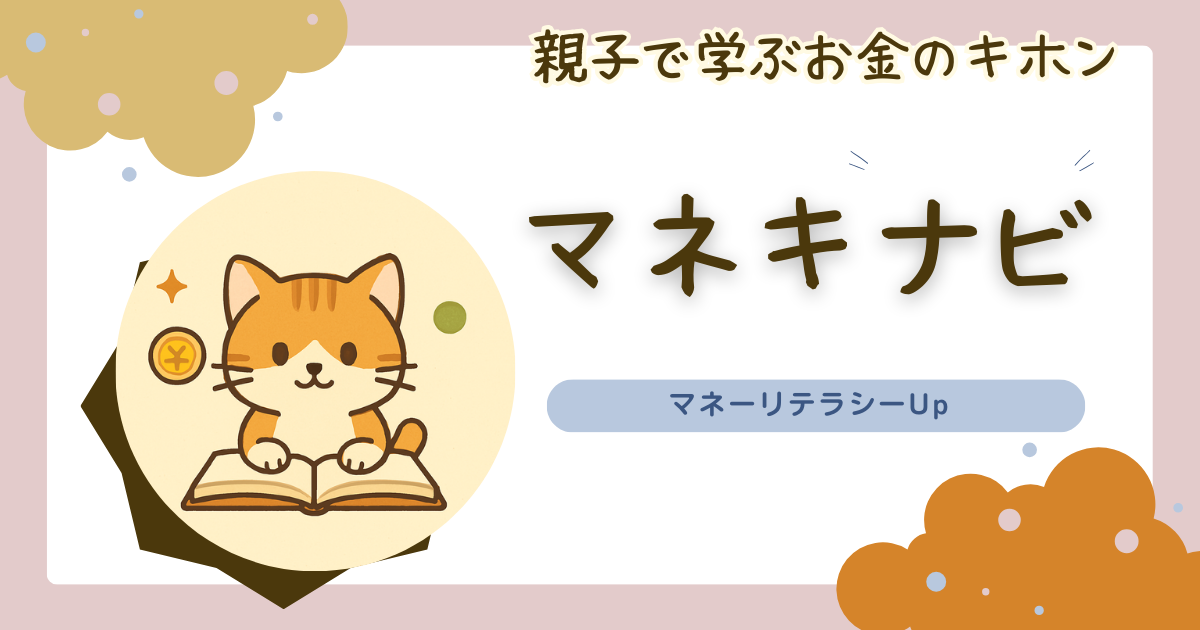

コメント