社会保険料って、なんでこんなに引かれるの?|親が子に伝える“見えないお金”の仕組みとこれからの備え
給料からたくさん引かれている「社会保険料」。 「え、そんなに稼いでるわけでもないのに…?」と思うほど、手取りが減る感覚はありますよね。 でも、子どもに「なんでこんなに引かれるの?」と聞かれたとき、うまく説明できる自信はありますか? この記事では、「社会保険料ってなに?」「払ったらどうなるの?」「将来返ってくるの?」という問いに向き合いながら、 親として子どもに伝えられる視点とヒントを整理していきます。
「なんでこんなに引かれてるの?」給与明細の“見えないお金”を知る
健康保険・年金・雇用保険…どれも「社会保険料」って呼ばれる
社会保険料とは、病気・ケガ・老後・失業といった、人生の困りごとに備えるための「保険」のようなもの。 代表的なものはこの3つです: – 健康保険:医療費を3割負担に抑える仕組み – 厚生年金:将来の年金や障害時・遺族への備え – 雇用保険:失業したときや育児休業中に支給される どれも「将来必要になるかもしれないときのために、今みんなで支え合ってお金を出し合う」という仕組みなんです。
月いくら?会社がどれだけ負担してる?
たとえば月収25万円の会社員であれば、毎月およそ4〜5万円前後が「社会保険料」として差し引かれています。 でも実はこの金額、会社も同額を負担しています。 つまり、「本人と会社で、あわせて月8〜10万円の保険料を支払っている」状態。 それだけ、社会保険という仕組みが大きくて、たくさんの人に支えられているということです。
税金とはどう違うの?
よく「税金と何が違うの?」と聞かれますが、簡単に言うと—— – 税金:国や自治体に納めて“公共のため”に使われる – 社会保険料:自分や家族・社会の「備え」として“目的が決まっている” つまり、税金よりも「直接的に自分に返ってくる可能性が高いお金」と言えます。
【伝え方】「いま使う人」と「いつかの自分」を支えるしくみなんだよ
社会保険料は、いま困っている誰かを支えると同時に、 いつか自分が困ったときにも助けてもらえる“支え合いの仕組み”。 「払ったぶん損してる気がする」と感じることもあるかもしれません。 でもそのおかげで、病気でも働ける、子どもが生まれても生活できる、老後も最低限の生活が守られる。 “見えにくいけれど、大事なお金”として、子どもにもぜひ知ってほしい内容です。
「年金って、将来もらえるの?」と言われたらどう答える?
年金制度は“仕送り式”|いまは現役世代が高齢者を支えてる
年金は「自分が払ったぶんを将来受け取る貯金」ではなく、 現役世代が、高齢者世代を支える“仕送り型”の仕組みです。 そのため、今払っている年金保険料は、 ほとんどが「今の高齢者の生活費」として使われています。 だからこそ、「今の若い人は、将来もらえないかも」と言われるわけですが、 それでも制度自体がすぐになくなることはありません。
少子高齢化でどうなる?もらえないリスクも本音で話す
日本は世界でもトップレベルの「超少子高齢社会」。 現役世代の人口が減り、高齢者が増えているため、 年金制度はかなり厳しいバランスになっています。 – もらえる金額が減るかもしれない – 受け取り年齢が引き上げられるかもしれない ただし、それは「まったくもらえなくなる」という意味ではありません。 むしろ、「どんな状況でも最低限もらえる」という意味で、 国が用意する“最後のセーフティネット”とも言えます。
でも、無視していい制度ではない理由
「将来もらえないかもしれないなら、払わない方が得?」 そう考える人もいますが、それには大きな落とし穴があります。 – 年金には「障害年金」「遺族年金」という保険の機能もある – 納付していないと、将来の生活保護などにも影響が出る可能性 – 無年金状態になると、民間保険ではカバーできないリスクを背負うことに 払う・払わないではなく、“どう活かせるか”で考える視点が必要です。
【伝え方】「もらえないかも」は、「もらえない」って意味じゃない
「年金なんてどうせもらえないよ」と言いたくなる気持ち、わかります。 でも、そこをそのままにせず、制度の仕組みと課題をセットで伝えることが大切です。 – もらえる金額は確かに減るかもしれない – でも、もらえないわけではない – そして、いま払っているからこそ将来の「選択肢」を持てる そんなふうに伝えると、ただ不安を押しつけるのではなく、 制度を使う力=生きる力につながっていきます。
「学生は払わなくていいって本当?」親として備えておきたいこと
学生納付特例=“猶予”であって“免除”ではない
大学生など所得の少ない人は「年金を払わなくていい制度がある」とよく言われますが、 正しくは「払わなくていい」ではなく、“今は払わなくていい”=猶予制度です。 これが「学生納付特例制度」。 申請すれば一定期間は保険料の支払いを猶予されますが、将来の年金額には反映されません。 つまり、この期間の分を“追納”しなければ、年金は減る(あるいは最低額になる)ということです。
追納しなかったらどうなる?将来の年金額や障害年金に影響も
猶予された分をあとで払わなかった場合、将来の受け取り年金額は減ってしまいます。 さらに、万が一の事故や病気で「障害年金」や「遺族年金」が必要になったとき、 納付要件を満たしていないと、そもそも受け取れないケースも。 「あとで払えばいいや」ではなく、“払っていない間にもリスクがある”ということを知っておく必要があります。
就職後や奨学金との兼ね合いもふまえて考える
追納には期限があり、10年以内でないと支払いができなくなります。 また、学生時代の追納が就職後の生活費や奨学金返済と重なると、家計を圧迫することも。 – 就職後すぐに負担が増えるのはきつい – 一括で払えないと結局“払わずに終わる”可能性もある だからこそ、「先送りしたお金が、あとでどう戻ってくるか」を早めに考えておくことが大切です。
【伝え方】“いま払わない”なら“あとでどうするか”まで一緒に考えよう
学生納付特例はありがたい制度ですが、 「制度を使う=納得して選ぶ」という意識がないと、あとで困ることにもつながります。 – 免除じゃなく、あくまで猶予 – 払わなかったぶんは、将来の備えが薄くなる – 親子で一緒に“いつ・いくら・どう払う?”を考えるのが大切 一時的な節約のつもりが、「本当は守ってもらえるはずだった未来」を手放してしまうことのないように—— 制度は「逃げる」ものではなく、「活かす」ために使っていきましょう。
「子どもにどう伝える?」社会保険と“これからの付き合い方”
「損か得か」より、「どう活かせるか」の視点へ
社会保険について話すとき、 「どうせ損する」「払ったぶん返ってこない」などの“損得”で語られがちです。 でも、本当に大事なのは、 「制度をどう活かすか」「どう備えるか」の視点。 – 病気やケガで入院したとき – 親が働けなくなったとき – 就職がうまくいかなかったとき 社会保険は、「もしも」のときに、人生の選択肢を残す力になる制度です。
誰かを支えることが、めぐって自分を守ることになる
社会保険は、“助け合いの仕組み”です。 今の自分が使わないからといって不要なのではなく、 「いま困っている誰かを支えること」が、「いつかの自分を守る力」にもなる。 そうした視点を、子どもにもわかる言葉で伝えられるようになると、 お金の教育としても、社会の一員としても、とても大きな一歩になります。
制度の仕組みを“自分ごと”として伝える工夫
制度の説明は難しくなりがちですが、たとえば—— – 「入院3日で10万円かかるところが、社会保険で3万円ですんだ」 – 「おじいちゃんがもらってる年金も、働いてる人の保険料から出てるんだよ」 – 「育休中も給料の代わりに支給があって、ちゃんと生活できたよ」 こうした身近なエピソードを交えて話すと、 “自分にも関係あること”として、子どもの理解が深まります。
【まとめ】“見えないお金”の意味を知って、納得して払える人に育てよう
社会保険料は、見た目の「手取り」を減らす存在かもしれません。 でも、それは「未来を支える土台をつくっているお金」でもあります。 子どもにその意味を伝えることは、 – 自分で選ぶ力 – 社会に参加する力 – 生き抜く知恵 を育てることにもつながります。 “ただ払ってるだけ”じゃなく、理解して使えるように。 親の言葉でそれを伝えられたら、それだけで大きなマネーリテラシー教育になります。

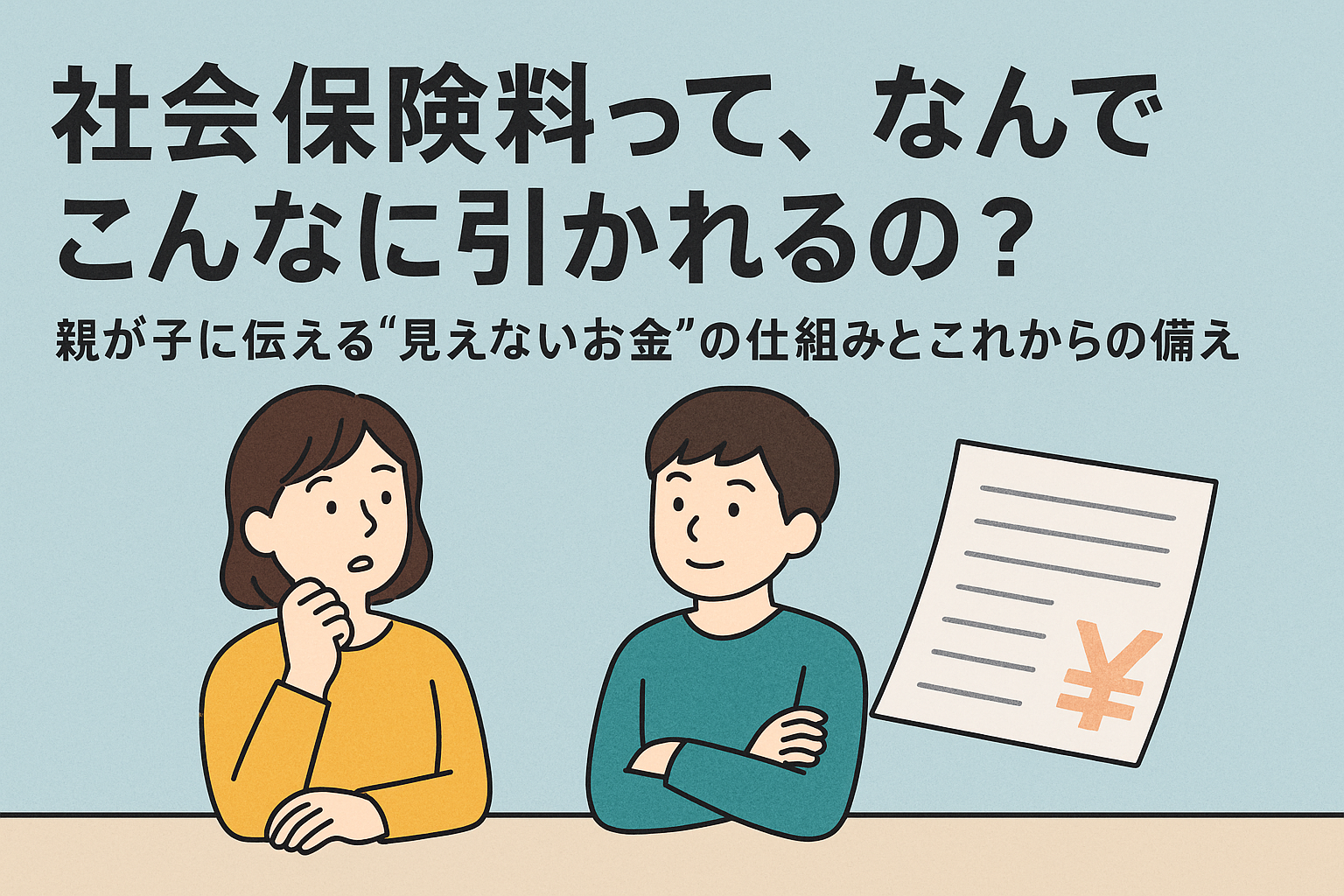

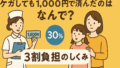
コメント