“推し活”が止まらない…!?中学生の“課金沼”にどう向き合うか
「また新しいグッズ買ってる…」
「課金って言葉、こんなに軽かったっけ?」
中学生の「推し活」が止まりません。
アニメキャラ、アイドル、配信者、VTuber、ゲーム…
“推し”を応援することが当たり前になり、日々のおこづかいの多くがそこに使われています。
「自分の好きなものに熱中するのは良いこと」
でも、「このままで大丈夫なの?」とモヤモヤする親の気持ちも本物です。
「推し活」って何?子どもにとってどれほど大きい存在?
グッズ・課金・抽選…「応援」にお金が必要な時代
推し活とは、「応援する人やキャラの活動を支えたい」という気持ちからくる行動のこと。
例えば:
子どもたちは“応援=お金を使うこと”が前提の文化の中で育っています。
なぜそんなに熱中する?「共感課金」の心理とは
今の推し活は、「憧れ」だけでなく「共感」が軸になっています。
「自分も頑張ろうと思えた」「辛いときに励まされた」
そうした感情のつながりが、課金や購入という“行動”に自然とつながっていくのです。
大人で言えばどんなものに近い?
「なんでそんなにお金使うの?」と感じたとき、大人の行動に置き換えてみると納得できることがあります。
つまり、子どもたちの推し活も、“自分らしさ”や“所属感”をつくる手段として機能しているのです。
「必要なの?」と思ったときに考えたい“価値の違い”
親から見ると、「それ、ほんとに必要?」と思ってしまうこともあるでしょう。
でも、子どもにとっての“推し”は、感情・自信・つながりの源になっていることもあります。
だからこそ、まずは“否定しない理解”が大切。
そのうえで、「どこまで」「どう使うか」を考えていく必要があります。
次は“ルールだけでは防げない課金”と向き合うための、考える力を育てる具体的な工夫を紹介します。
ルールだけじゃ防げない。推し活に“考える余白”を
「月のおこづかいの中でやりくりしてね」
「課金は〇〇円までにしよう」
こんなルールを決めたのに、結局守れない。
あるいは、守ってはいるけれど「本当に考えて使っているの?」と感じる。
──それもそのはず。
ルールは、感情の熱量には勝てないことがあるからです。
ではどうすれば、“欲しい”に流されない力を育てられるのでしょうか?
ここでは、実践しやすく、かつ子ども自身が「自分で選ぶ」ことを意識できる工夫を紹介します。
① 推し活の支出を「必要」「満足」「後悔」の3軸でふりかえる
グッズや課金をしたら、あとで簡単に「満足度」を記録してもらいましょう。
この3つの軸でふりかえるだけで、「なんとなく買う」から「考えて選ぶ」への第一歩になります。
② “無条件に買う”をやめる。「応援には計画も必要」と気づかせる
「推しのためだから」と、全部にお金を使っていたらきりがありません。
「全部応援したいけど、今はどれを選ぶか考えてみよう」
この声かけだけでも、「応援=なんでも買う」から「応援=戦略的に支える」という考え方に切り替えるきっかけになります。
③ 推し活専用の「ログ帳」や「活動メモ」をつけてみる
好きなノートやアプリで、「何にいくら使ったか」「そのときどう感じたか」を簡単に記録。
記録がたまると、自分の行動パターンが見えてきます。
- 「イベント前はつい財布がゆるくなるな」
- 「買っても封を開けてないグッズがある」
こうした“振り返り”は、感情をお金に流されにくくするブレーキになります。
④ 自分の推し活ルールを“家族にプレゼン”してもらう
「わたしはこういう考えで推し活してます!」というプレゼンを、家庭内でしてもらうのもおすすめ。
自分で決めたルールや支出の根拠を説明することで、「納得して選んでいる」意識が育ちます。
また、親も「そういう考えだったんだ」と子どもの視点を知ることができます。
次はこの推し活の熱量を“学び”につなげる方法をご紹介します。
自由研究やプレゼン、探究型教材など、将来の力になる活かし方とは?
“推し活”を「学び」に変える──自由研究にもなる応援スタイル
推し活に熱中するエネルギーは、ただの“消費”で終わらせるにはもったいない。
その熱量を「学び」に転換することで、自己理解・表現力・探究心を伸ばすことができます。
推し活を“自由研究”に変えてみよう
たとえば、こんなテーマで自由研究やプレゼンができます:
どれも、子どもが“好き”から始めて、調べて・考えて・表現する流れが自然に生まれます。
家庭内の“作品発表”が次のモチベーションに
できあがったら、学校に提出しなくてもOK。
家族にプレゼンしたり、アルバムに残したり、非公開でSNSにアップするだけでも、達成感や自信につながります。
「応援でお金が動く仕組み」を学ぶ入口にも
さらに一歩踏み込めば、推し活は「経済」や「社会」の学びにもつながります。
これらを親子で一緒に調べることで、「お金がどう流れているのか」を体験的に理解できます。
好きだからこそ、未来につながる
推し活は、感情と行動がリンクする貴重な体験です。
そこに「選ぶ力」や「考える習慣」「伝える表現」が加われば、未来の選択肢そのものになります。
「浪費してばかりで心配」ではなく、
「この熱量をどう育てるか?」という視点で見つめ直してみませんか?


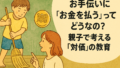

コメント