自分の“お金のクセ”を知るワーク|子どもの行動から見える“金銭性格”とは?
「またお金、すぐ使っちゃってた…」 「なんであの子と遊ぶときだけ、急に使いすぎちゃうんだろう?」 お金の使い方には、その子なりの“クセ”や“感情の動き”があらわれます。 この記事では、親が子どもの金銭行動を一緒にふりかえりながら、「自分って、どういうタイプ?」を考えるワークを紹介します。 使い方そのものよりも、「なぜそう使うのか?」という心の動きを見つめていくことで、 子ども自身が“自分らしさ”に気づき、自分を守る判断軸をもてるようにサポートします。
子どもの“お金のクセ”って、どこに出るの?
ひとりでいるとき vs 友達といるときの使い方の違い
子どもがお金をどう使うかを観察すると、ひとりのときと誰かと一緒のときで使い方が違うことに気づくかもしれません。 – ひとりでいるときは買わないのに、友達といると勢いで買ってしまう – 友達の前では“いい顔”をしたくて、つい多めに出してしまう こうした行動には、“その子の性格”と“人間関係での役割”がにじみ出ています。
「なんでこれ買ったの?」が親子のヒントになる
「これ、ほんとに欲しかったの?」ではなく、 「なんでこれにしたの?」「どんな気持ちだった?」と聞いてみることで、 その場での気持ちや、誰かとの関係が見えてくることがあります。 お金の選択は、感情の反射でもあります。 小さな買い物の中にある、子どもなりの“意味”をていねいに拾ってみましょう。
“お金の使い方”は“その子らしさ”の表れ
使いすぎ、慎重すぎ、あげすぎ——どれもダメではありません。 そこには「楽しい時間を優先したい」「友達と仲良くいたい」「迷惑をかけたくない」といった、その子なりの気持ちがあるはず。 まずは「そのクセ=その子の思いやりや不安の形かもしれない」と受け止めてあげること。 それが、“自分を知る力”を育てる第一歩になります。
診断してみよう!お金の使い方からわかる“金銭性格タイプ”
【質問に答えてみよう】あなたの“お金の使い方”どんな感じ?
次の質問に、子どもと一緒に○×で答えてみましょう(あくまで目安です)。
1. もらったお金はすぐに使いたくなる
2. 誰かが困っていると、つい自分のお金を使ってあげたくなる
3. 買い物で「みんなと同じじゃないと不安」と感じたことがある
4. お金を使うとき「後で困らないかな?」と考える方だ
5. つい見栄を張って、ちょっと高いものを選んでしまうことがある
6. 友達と遊ぶとき、自分が出す側になることが多い
7. ほしいものは、何日か考えてから買うようにしている
○が多い項目から、子どもの“金銭性格”の傾向を一緒に見てみましょう!
【診断結果】あなたはどのタイプ?
🟡 勢いタイプ(1, 5に○が多い)
→ 欲しい!と思ったら即行動。失敗から学ぶ力を育てよう。
🟢 応援タイプ(2, 6に○が多い)
→ 人のために使うのが得意。でも無理は禁物。
🔵 同調タイプ(3に○)
→ 周りに合わせた選択をしがち。自分の基準を育てて。
⚪ 慎重タイプ(4, 7に○が多い)
→ じっくり考える安心派。使う“楽しさ”も大事にしてね。
タイプに優劣はありません。それぞれに良さと注意点があることを、親子で共有してみましょう。
「どれが正解」じゃなく、「気づけたこと」が大事
この診断は、子どもを型にはめるためのものではありません。 「自分ってこういうとこあるかも」と気づけたことが、すでに大きな一歩。 どんなクセも、“強み”にも“課題”にもなり得るからこそ、知っておくことが大切です。
金銭性格は、友達づきあいや“断る力”にも影響する
「あげちゃう子」「合わせる子」「断れない子」それぞれの背景
お金の使い方は、そのまま“人との付き合い方”にもつながります。 – 気前よくなんでも「あげちゃう子」は、仲良くなりたい気持ちが強いのかも – まわりに合わせて無理に使う子は、不安や寂しさを抱えているかもしれない – 断れずに出し続ける子は、優しさの裏に遠慮や自信のなさがあることも クセを責めるのではなく、「なぜそうしてるんだろう?」と背景に目を向けてあげると、関係のトラブル予防にもつながります。
「あの子と遊ぶとお金が減る…」関係性の変化にも目を向ける
お金をめぐる関係が「偏り」になっていないかにも注意が必要です。 「この子と遊ぶときだけ、毎回お金を出してる気がする…」 そんな気づきがあれば、それは“相性のサイン”かもしれません。 「嫌いになる」ではなく、「少し距離を取る」「別の遊び方を提案する」など、関係を大きく壊さずにバランスを取り直す工夫も大切です。
親が“距離感”の言語化をサポートしてあげよう
子どもにとって、「お金のことで関係を変える」のはとても勇気がいります。 だからこそ、親が「どう思った?」「どうしたい?」と気持ちを引き出しながら、 「こういうときは、“少し離れてみる”って選択もあるよ」と言葉にしてあげることが大切です。 感情と距離感をセットで整理できるようになると、お金のトラブルだけでなく、人間関係のストレス全体が軽くなるかもしれません。
自分の“クセ”に気づけたら、“選べる子”になる
「つい使っちゃう」も「断れない」も、クセとして知っていれば大丈夫
お金を使いすぎるのも、あげすぎるのも、合わせてしまうのも、ダメなことじゃありません。 大事なのは、「自分はそうなりやすいんだ」と気づいておくこと。 気づいていれば、同じ場面で「どうしようかな」と立ち止まる余裕が生まれます。 クセは直さなくていい。“知っていること”が、いちばんの武器になるんです。
自分の行動に理由がつくと、ブレずに判断できる
「なんでそうしたの?」に、自分なりの理由があると、人の意見や空気に流されにくくなります。 – 「自分のお金は、こういうときに使いたい」 – 「これは自分にとって大事な買い物だった」 – 「今は使わないって決めてたから、やめた」 “自分で選んだ”という実感が、あとから自分を守ってくれます。
子ども自身が「自分を守るルール」を持つために
親が作ったルールを守ることから始まって、 やがて子ども自身が「自分のルール」を持てるようになる。 それが金銭教育のひとつのゴールです。 「これ、自分にとってよかったかな?」とあとから考えられる子に。 そして、「次はこうしてみよう」と自分で選べる子に。 その力は、お金だけじゃなく人生のいろんな選択でも役に立ちます。

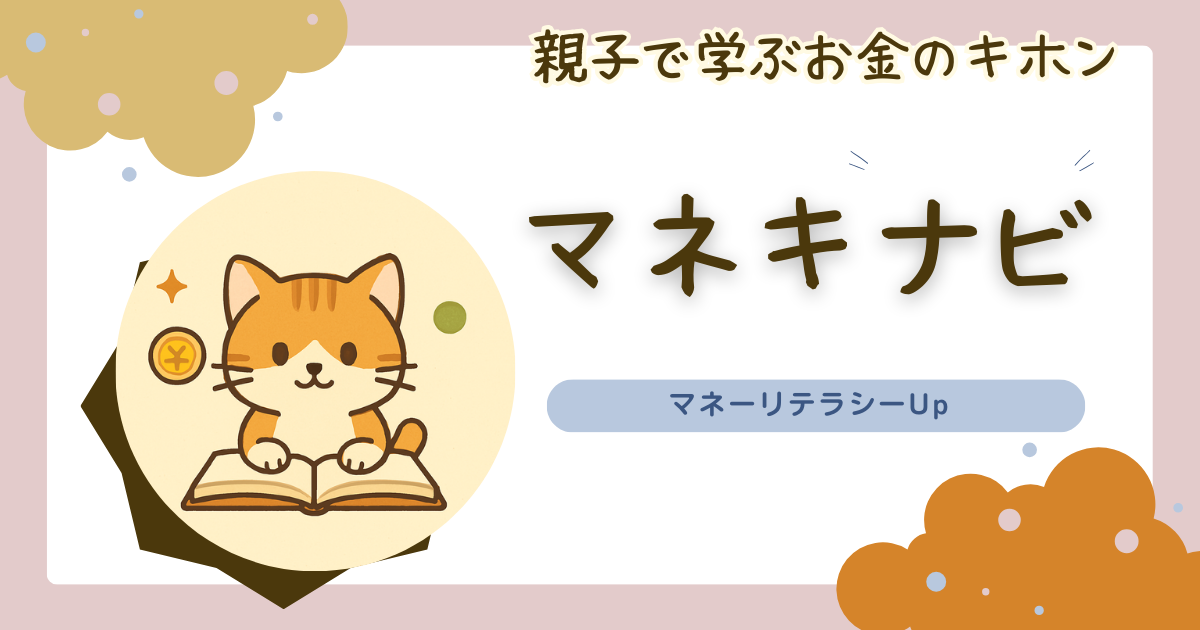

コメント