“おこづかい稼ぎ”は悪じゃない!子どもが楽しみながら実践できる4つの収益体験
「子どもに“稼ぐ”ことなんて、まだ早いんじゃないか……」
そんなふうに感じている親御さんも多いかもしれません。特に最近では、投資や副業といったキーワードが子どもの教育にも登場するようになり、「本当に必要なの?」「危なくないの?」という声もよく聞かれます。
しかし実際には、「おこづかいを“もらう”」だけでは見えてこない、“お金の成り立ち”や“価値の実感”を育むには、「自分で得る」経験がとても大切です。
今回は、子どもでも安心して取り組める「収益体験」を4つご紹介します。お金の大切さを“体験”から学ばせたいと感じている親御さんにこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。
なぜ今、“子どものおこづかい稼ぎ”が注目されているのか
おこづかいだけでは学べない“価値と対価”
おこづかいは、親が子どもに与えるもの。もちろん管理の練習にもなりますが、「どこからどう得たお金なのか?」という感覚は、なかなか育ちにくい側面もあります。
一方、“自分で得る”経験を通すことで、「努力と結果のつながり」や「欲しい物のために自分ができること」など、より主体的なマネー感覚が育ちます。
投資教育の前に、“働いて得る”体験が必要?
最近はNISAや投資教育の話題が増え、「子どもにも金融リテラシーを」と語られるようになってきました。
ただ、その前提として必要なのが、「お金は“働いて得るもの”だ」という実感です。これがないまま“投資でお金が増える”という知識だけが先行してしまうと、現実とのズレやリスクに対する感覚が育たない恐れも。
だからこそ、小さな収益体験が、子どもにとっての土台づくりになるのです。
よくある親の不安「早すぎるのでは?」「危なくない?」
もちろん、「子どもが自分でお金を稼ぐなんて…」と感じるのは自然なことです。特にインターネットを使う活動には、トラブルや不正利用への心配も尽きません。
そこでこの記事では、親がしっかり見守りながら、一緒に楽しめる体験を紹介していきます。
「早い段階からお金に触れさせたいけど、どうすれば安全に教えられるかわからない」──そんな親御さんのヒントになれば嬉しいです。
親子で取り組める!4つのリアルな収益体験
ここからは、子どもでも安心して取り組める「収益体験」を4つご紹介します。どれも親がそばでサポートしながら、子どもの興味や得意を活かせる体験です。
① フリマアプリでの不用品販売
家の中にある「もう使わないけれど捨てるには惜しい」ものを、子どもと一緒にフリマアプリで出品してみましょう。例えば、おもちゃや本、子どもが描いたイラストなども立派な出品物になります。
子どもの“商品説明文”が意外とクリエイティブ
「どうやって説明したら売れるかな?」と考える中で、子どもならではの視点が生きてきます。写真の撮り方や言葉選びなど、伝える力も育ちます。発送作業などは親が担当することで、安全面もクリアできます。
② 動画・音声のナレーションや編集補助
動画や音声の編集に興味がある子には、ナレーションやちょっとした編集作業を「親の依頼」としてやってもらうのも手。例えば、家族旅行の動画にナレーションを入れてもらったり、簡単なテロップをつけてもらうなど。
親が発注者側になって「報酬を払う」体験を
これは“お手伝い”とは違い、「依頼された仕事に対して成果を出す」という体験になります。子どもは「仕事としての責任感」を学び、親も評価や報酬を通して、金銭のやり取りのリアルさを伝えることができます。
③ ゲーム×レビューで「おこづかい」企画
「うちの子、ゲームばっかりで…」という悩みを逆手にとって、「レビューを書く」という収益体験にしてみましょう。プレイ後に「面白かった点」「改善点」などを文章にまとめて発表します。
楽しみながら“検証力”を身につける
これはブログやSNSでの発信にもつながりますが、まずは「親にプレゼンしておこづかいをもらう」という形でもOK。ゲームや趣味が“稼ぎ方の種”になる体験は、自己肯定感にもつながります。
④ お手伝い“じゃない”、ミッション
いわゆる“お手伝い”とは違い、「家庭内のミッション」として業務を依頼し、金額を決めて報酬を支払う体験です。たとえば「来客前の部屋のコーディネート」や「冷蔵庫の整理整頓」など、ちょっと工夫が必要な内容がおすすめ。
家計の中で“任せる”仕事には報酬がある
「任せる」という視点を持つことで、子どもも自然と責任感を持つようになります。これは単なるお小遣い制よりも、「仕事=価値の提供」という意識が育ちやすくなります。
まずは「収益体験」の小さな一歩から
ここまでご紹介した4つの体験は、すべて「すぐにできる」「親が関与しやすい」ものばかりです。子どもの年齢や性格に合わせて、無理なく始めてみることが大切です。
親が「管理者」になるべき場面と、その伝え方
とくにインターネットやお金のやりとりが発生する場合は、必ず親が“監督者”として関わることが基本です。ただし、なんでも口を出すのではなく、「ここは任せるけど、ここは一緒に見守るよ」というスタンスが◎。
例えば、フリマアプリの出品内容は一緒に確認し、発送や連絡は親が代行する…など、段階を踏むことで「自分でできるようになる実感」を積み重ねることができます。
子どもの気づきと成長を「記録」する
実際に稼いだ金額や、そのために工夫したことなどは、ぜひノートやアプリに記録させてみてください。「自分はこれが得意だった」「もっと工夫すればよかった」という振り返りが、将来の学びや職業観につながります。
親としても、「やらせてみてよかった」と感じられる瞬間がきっとあるはずです。
継続的に学べる機会として──体験講座や家庭向け教材も
今回紹介したような体験をもっと体系的に学べる場として、次のようなサービスもおすすめです:
- ✔️ 親子で学べるマネー体験講座(ワーク形式で“稼ぐ・使う”を体感)
- ✔️ 小学生〜中学生向け家計管理シート(PDFで無料配布 or 有料教材リンク)
- ✔️ 証券口座開設を考える親向け「NISAガイド」(将来に備えての準備)
「お金の勉強はまだ早い」と思われがちですが、遊びや体験を通して“自分ごと”として学べる今こそ、チャンスかもしれません。
少しずつ、でも確実に。
お金を通じた“生きる力”を、家庭の中から育んでいきましょう。


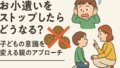
コメント