“うちはうち”は通じない?お金格差と子どもの常識が塗り替えられる前に
「〇〇くん、毎週おこづかい1,000円もらってるんだって」
「ゲームの課金も自由なんだってさ」
そんなことをポロッと子どもに言われて、
「うちはそんな感じじゃないよ」と返した瞬間、空気がピリついたことはありませんか?
今の子どもにとって「友達の家」が“基準”になっている
昔は「うちはうち、よそはよそ」で済んでいた──そう思っていた私たち親世代。
でも、今は違います。
子どもにとっては、「友達の家」が“比較対象”ではなく、“社会の常識”そのものに映っていることが多い。
それしか見えていないから、「自分だけ違う」が、「自分だけ間違ってる」に直結しやすいんです。
「違う」はすぐに「損してる」に変わる
「なんでうちはダメなの?」「どうしてもらえないの?」
その背景には、“違う”という事実を、子どもが“損してる”と感じる感覚があります。
理屈じゃない。感情の話。
子どもは「損した」と感じると、その気持ちが親との距離にもつながってしまう。
「理解してもらえない」「うちは遅れてる」そんなイメージがついてしまうことも。
親が思う以上に、子どもの世界は“狭くて深い”
学校、友達、動画、SNS──
今の子どもたちが接している世界は、広いようで実はとても限定的。
でも、その中での情報は昔とは比べものにならないほど具体的でリアルです。
昔は「〇〇ちゃんのお家はね…」という“噂レベル”での比較が中心でした。
でも今は、「あの子、Switch買ってもらってた」「YouTubeで開封動画見た」「昨日ガチャ10連してた」──
映像で、金額で、実感で届いてしまう。
だからこそ、子どもにとっては「よその家庭の当たり前」が、自分の常識を塗り替えてしまうほどの影響を持つ。
次はそういう時代に親ができる、
“話し方”よりも“話す姿勢”の工夫について考えていきます。
話し合いの目的は、納得させることじゃない
子どもから「どうしてうちはこうなの?」と聞かれたとき、
親としてはできるだけ納得してほしいと思ってしまう。
でも実は、子どもを“納得させる”のがゴールじゃなくていいのかもしれません。
ルールは変わってもいい。でも考え方は残しておきたい
おこづかいの額や使い方、家庭の方針は、
成長や生活の変化に合わせて変わっていくのが自然です。
でも、「なんとなく」で変わっていくのと、
考え方があったうえで柔軟に動かすのとでは、伝わり方がまるで違う。
「一律〇円」じゃなくて、
「今は〇円でこういう理由なんだよ」があるだけで、納得はしなくても“残る”ものがあるんです。
「うちはこう思ってる」と伝えることが大事
「うちは違うよ」よりも、
「うちはこう考えてるよ」と伝える方がずっと響く。
例えば:
- ・「全部渡すより、選ぶ練習をしてからにしたいんだ」
- ・「節約が正しいというより、工夫して使ってほしいと思ってる」
こういうふうに、価値観を共有すること自体が大事な会話になります。
「どう思う?」と聞くだけでも、考えるきっかけになる
「納得してもらえないかもしれない」
そう思っても、「あなたはどう思う?」と聞いてみるだけでもいい。
たとえ不満が返ってきても、
そのやりとり自体が“考えるきっかけ”になっていることがあるからです。
いつか思い出すかもしれない。
そのために、「ちゃんと話した」という記憶があるかどうかは、意外と大きい。
次は親自身も迷いながら向き合うことについてお話しします。
親も迷っていい。“一緒に考える姿勢”が大事
「毎月のおこづかい、いくらが適正か?」
「何に使わせるか、どこまで任せるか?」
正直に言えば、親だって明確な根拠があるわけじゃないことが多いですよね。
「金額の根拠」なんて実はあいまいでいい
子どもの年齢、周りとのバランス、今の生活──
いろんな要素を“なんとなく”で考えて決めているのが普通です。
それでもいい。
大事なのは、その時点でどう考えてるかを、ちゃんと話せること。
押しつけでも誘導でもなく、ちょうどいい距離感を探す
「ダメって言い切るのも違う気がする」
「でも全部任せるのも心配…」
そんなふうに、真ん中のグレーゾーンで揺れてる親は多いと思います。
だからこそ、“あいだ”の選択肢を探すというスタンスが大事。
ガチガチのルールでもなく、丸投げでもなく、
「今はこうだけど、また話し合おうね」という柔軟さ。
「とりあえず話してみる」も立派な一歩
一発で答えが出なくてもいい。
「この金額でいいのかは正直わからないんだけど、
どう思ってるかだけ聞かせてくれる?」
そんなふうに、親も“迷ってる”ことをちゃんと伝えることが、
むしろ信頼につながることもあります。
大事なのは、親も準備して向き合おうとしてること
「子どもに話してもわからないから」と思わずに、
話せる準備を親の側でもしておくことが大切です。
そしてときには、家族で「今のルールってどう思う?」と見直してみるのもおすすめ。
家庭によって、子どもによって、ベストな答えは違う。
でも、一緒に悩んで考えている姿勢そのものが、子どもにとっての安心になる。
“うちはうち”を、ただの決まり文句で終わらせないために。
いま、親ができることは「完璧な正解を持つこと」じゃなく、
話し合える関係をつくることなのかもしれません。


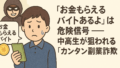

コメント