「使いすぎた」「知らないうちに」電子マネーの落とし穴と対策──“便利”の裏にあるズレに、親子で気づくために
「そんなに使った覚えはないのに、残高がない…」
PayPayやSuicaなど、電子マネーは便利な反面、子どもにとって“使った感覚”が残りにくいツールでもあります。実際、ある調査では「子どもが電子マネーでお金を使いすぎるのでは」と不安を感じている親が59%にのぼっています(※PR TIMES調査より)。
さらに、国民生活センターには、子どもがオンラインゲームで高額課金をしてしまったという相談も。中には、親のスマホで100万円以上の決済が行われていたケースもあるといいます(※TBS NEWS DIG)。
こうしたトラブルは一部の例に思えるかもしれませんが、日常のおこづかいでも「つい使いすぎた」「気づいたら残高がゼロだった」ということは、決して珍しくありません。
この記事では、電子マネーの“バグりやすい瞬間”を通して、金銭感覚がどうズレてしまうのかを探りつつ、親子で取り組めるシンプルな対策をご紹介します。
なぜ電子マネーは「使いすぎ」に気づきにくいのか?
履歴は見えるのに、感覚は残らない
電子マネーは、利用履歴がアプリなどに残るため「見える化」されているように思えます。けれど実際には、子どもが自分で確認する習慣がなかったり、「あとで見ればいいや」でスルーしてしまったりと、“気づけない支出”になりやすいのが現実です。
しかも1回の金額は300円、500円と少額でも、週に数回積み重なると2000円、3000円というケースもざら。「そんなに使ったつもりはない」という感覚と、実際の数字とのギャップが生まれます。
Suicaの自動チャージも“支出感覚”をぼかす
たとえば、Suicaに自動チャージ設定をしていると、残高が減ってもすぐに補充され、子どもにとっては「減った感覚がない」状態になります。「ずっと使えてる=まだ残ってる」と勘違いしやすくなるのです。
履歴があっても、その場でお金が「手から出ていく」実感がないと、支出への意識は育ちにくい。これが現金との大きな違いです。
ゲーム課金やスタンプ購入は“記憶に残らない”消費
1クリックで買えてしまうゲーム内アイテムやLINEスタンプなども、使った感覚が残りにくい代表例です。「無料だと思ってたら実は課金だった」「お小遣いが減ってるのに理由が思い出せない」——そんな声もよく聞きます。
特に「無料お試し→解約し忘れ→自動課金」という流れは、子どもだけでなく大人でも引っかかりやすい落とし穴。便利さの裏にある“注意力”のズレを、意識できるかどうかが大きな分かれ目になります。
親ができる“バグり対策”は、実はシンプル
「見える化」と「タイミングのルール」をつくる
電子マネーの履歴は、自動で残ります。でも、履歴が“ある”ことと、“見る”ことは別。だからこそ、「週に1回、使い方を一緒にふりかえる」「チャージは週末だけにする」といった“使うタイミングのルール”が、感覚を整える助けになります。
ルールといっても堅苦しいものでなくてOK。「最近、なにに使ったっけ?」「お得だった?それともムダだった?」など、会話のきっかけとして履歴を見る習慣が大切です。
チャージも「毎週◯曜日に1000円まで」「使い切ったら次の週まで待つ」と決めておくと、メリハリが生まれます。
「金額」よりも「判断」をふりかえる
「いくら使ったか」よりも、「その買い物、どうだった?」と聞いてみることが大事です。たとえば、「あれは買って正解だった」「これはムダだったかも」といった自己判断の言語化が、金銭感覚をぐっと育ててくれます。
「じゃあ次に同じ状況だったらどうする?」と聞いてみると、子どもなりに考える視点が生まれます。この“予習的ふりかえり”が、次の行動に活きてきます。
大事なのは、間違ったことを咎めるのではなく、「考える習慣」を育てること。親は“答え合わせ”ではなく、“問いかけ役”に回るとちょうどいいバランスです。
「失敗しても大丈夫」が、学びになる
失敗体験こそ、いちばん残る
「残高がゼロで買いたいものが買えなかった」「買ってすぐ後悔した」——こうした小さな失敗は、実は最高の学びのチャンス。自分のお金で“やっちゃった”を経験できるのは、おこづかいの特権でもあります。
大人にとっては数百円の失敗でも、子どもにとってはインパクト大。思ったよりも残るし、「次はこうしよう」と自然に考えるきっかけになります。
「一度しくじって学ぶ」って、大人でも効果ありますよね。だからこそ、子どもにもそのチャンスをちゃんと渡してあげたいところです。
「怒られる」より「気づける」が育てる
使いすぎたとき、すぐ怒ったり禁止したりするのは簡単。でも、それだと「次にどうするか」の思考が育ちません。むしろ、「あーやっちゃったね!」くらいのテンションで、一緒にふりかえる方が、学びにつながります。
「じゃあ次はどうする?」「その買い物、またしたい?」——そんな問いかけで、子どもは自分なりの答えを探すようになります。
失敗談も、話せばネタになります。「前にゲームで使いすぎたときさ〜」なんて笑い話になるくらいが、ちょうどいいのかもしれません。
気づけたとき、電子マネーは“学びの道具”になる
電子マネーの便利さは、子どもにとっても魅力的。でも、だからこそ「つい使いすぎた」「いつの間にかなくなってた」も起きやすい。その感覚のズレに、親子で一緒に気づけるかどうかが大きな分かれ目になります。
履歴が残ること、使った場面をふりかえれることは、実は“最高の学びのチャンス”。大人のように完璧に管理できなくても、自分で考えたこと・選んだことは、ちゃんと子どもの中に残っていきます。
失敗しても大丈夫。「次はこうしよう」と思えたら、それが金銭感覚の育ち始め。怒るより、問いかけるほうが、きっと未来につながります。
電子マネーを“使いこなす力”は、いまからでも、ちゃんと育てられる。今日からできる一歩、親子で試してみませんか?

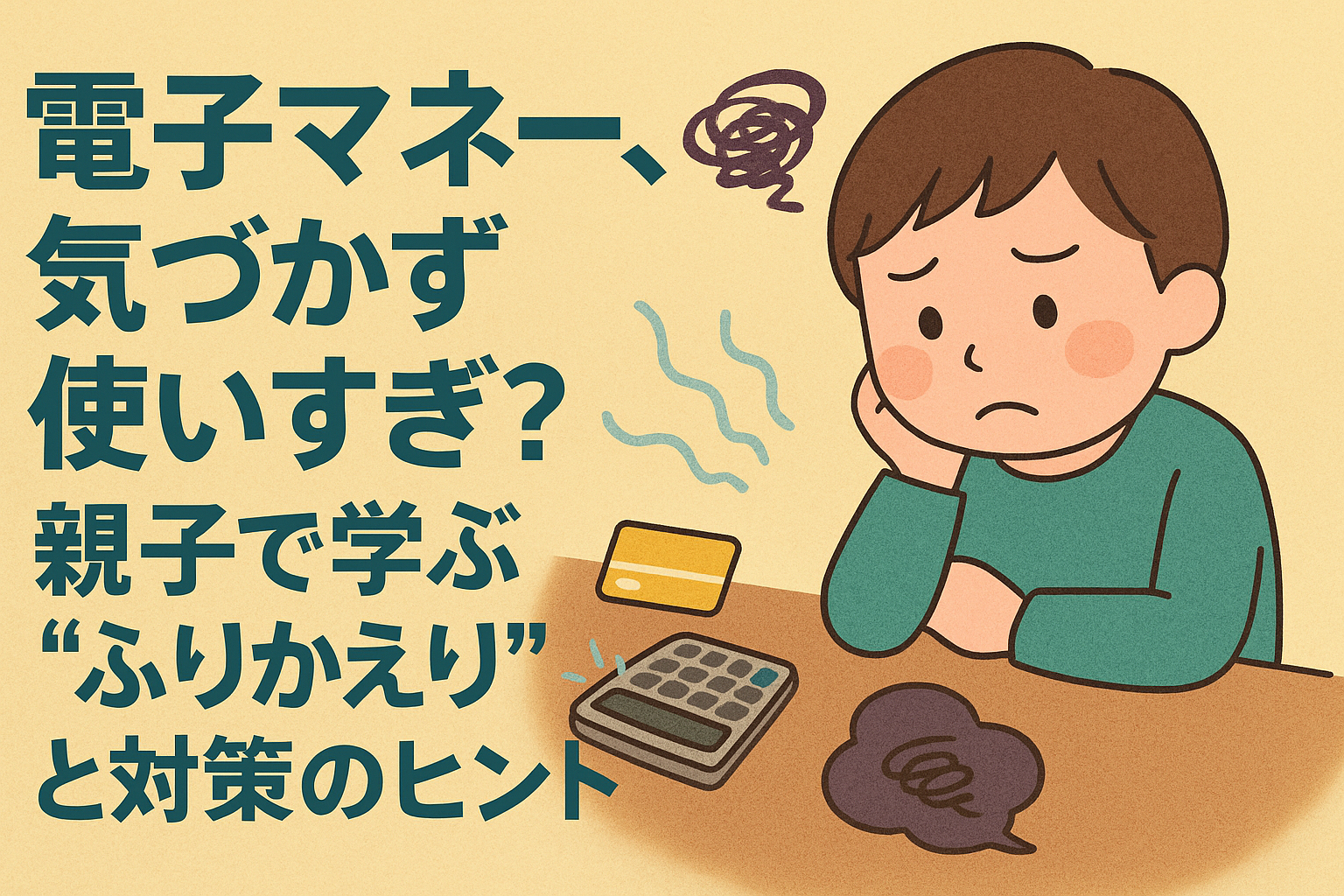
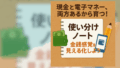
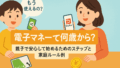
コメント