当たり前という危うさ──お小遣いをストップしたら何が起きた?
「お小遣い、まだ?用意してないとか言わないよね。」
子どもが発したその一言に、おいおいとなったことありませんか?
悪気があるわけではない。だけど、その言葉の奥にある“前提”が、親として気になってしまった──そんな経験を持つ方は、きっと少なくないはずです。
「お小遣いはもらって当然」
子どもにそう思われていると感じたとき、ふと疑問が湧きました。
――このままで、本当にいいのだろうか?
気づかぬうちに“当然の権利”になっていたお小遣い
「お小遣いくれないの?」「今日まだ」──何気ない言葉が刺さる
わが家では、お小遣いは毎月決まった日に渡していました。何年も同じスタイルだったから、子どもにとっては“生活の一部”のようなもの。
けれどある日、仕事でバタバタしていたこともあり、渡しそびれたタイミングで子どもにこう言われました。
「ねえ、お小遣い忘れてない?」
そのとき、胸の中で何かが引っかかったのです。「ありがとう」も「お願い」もなく、“当然の確認”として発せられたその一言に。
いつから“もらえることが当たり前”になったのか?
思い返せば、最初はお金の使い方を学んでほしくて始めたお小遣い制でした。
でも、忙しさの中で、いつの間にか“自動支給”になっていたのかもしれません。
親にとっては「教育の一環」だったはずが、子どもにとっては「給料日」と同じ感覚になっていたのです。
親のモヤモヤが積み重なった背景には、“伝えきれなかった想い”がある
お金の大切さ、使い方のコントロール。
そういったところを学んでほしかったはずなのに。
お小遣いは当たり前、無駄遣いも当たり前、足りなければ悪びれず理由をつけて追加要求する始末。
このままではいけないと感じた私は、思いきって「お小遣い、いったんストップしてみよう」と決めました。
子どもがどう感じるか、どう反応するか──不安もありましたが、そこから意外な気づきと小さな変化が生まれていくことになります。
お小遣いを止めたあとに起きた“混乱”と、変化を引き出す関わり
「えっ、なんで?」
「ずるい!それってひどくない?」
ストップを伝えたとき、子どもはすぐには納得しませんでした。
むしろ、怒りや困惑、そして不安が入り混じった反応が返ってきました。
「なんで?ひどい!」──最初は反発&交渉の嵐
それまで“もらえて当然”だったものが突然ストップされるわけですから、当然のことかもしれません。
「約束と違う」
「今月だって欲しいものあったのに…!」
怒る、交渉する──子どもなりに納得できない部分もあったでしょう。
「我慢してくれる」なんて期待しない。子どもにも子どもなりの言い分はある。
ここで大事なのは、「子どもが我慢できなかった」と責めることではなく、親がその反応を“当たり前のリアクション”として受け止められるかです。
そして、その“混乱”をどう成長の種に変えるかが、親の役割でもあります。
親ができる3つの関わり方(真似しやすいアプローチ)
① 「なぜストップしたのか」を一緒に話し合う
一方的に「やめた」と伝えるのではなく、「お金はもらえるものではなくて、どこからどうやって手に入るのか、一緒に考えてみない?」という問いかけをすることで、話し合いのきっかけが生まれます。
② 「じゃあどうする?」を一緒に考える
欲しいものを我慢させるだけではなく、「手に入れるにはどうすればいいか?」を一緒に考えてみる。
たとえば、これまでのあたりまえを見直させる、お手伝いなんかの自分の行動で得られる環境を与えるなど。
③「使い道・価値」を記録やクイズで振り返る
前にもらったお小遣いがどこに消えたか、どれだけ価値を感じたかを振り返るだけでも、「お金ってただの紙じゃない」と気づくことがあります。
ミニ家計簿や、選択クイズ形式で楽しく振り返る工夫も効果的です。
「じゃあ、自分でやってみようかな…」と変わったのは、そのあとだった
時間はかかりました。でも、少しずつ子どもから、「これやったらもらえる?」「◯◯のお手伝いってお金になる?」と、自分から行動や提案が出てくるように。
大きな変化ではないかもしれません。
でも、“もらうだけ”だった意識に、小さな「考える」芽が生まれた瞬間でした。
“前提”を壊した先に芽生える、お金の自立心
「なんで止めるの?」という反発から始まった、お小遣いストップ体験。
でもそこには、“与えないこと”でしか伝えられなかった学びがありました。
一時的な反発より“本質的な気づき”を育てたい
お金がもらえないと、子どもは一時的に怒ります。不安になります。
でも、そこから「どうしたら手に入るか?」「何に価値を感じるか?」を考え始めることで、“お金は湧いてくるものではない”という実感が育まれます。
ただ“もらう”から何かを通して”得る”へ──お小遣いを体験に変える
お小遣いの仕組みを「給付型」から「提案・実行型」にシフトすることで、子どもは自然と考えるようになります。
こうした体験は、「働くこと」「報酬」「貯める・使う・回す」という、マネーリテラシーの基本に自然につながっていきます。
“実践する家庭”を後押しするツール・教材・講座の紹介
「家庭内だけでやるのは難しい」「何を使って教えればいいかわからない」という方には、こんなリソースもあります:
「渡さない」のではなく、「伝わる仕組み」をつくろう
大事なのは、お小遣いを止めることではなく、
“お金の価値”を体験として伝えることです。
与える前提をやめたとき、親子に生まれるのは不満だけではありません。
そこには、「学び」「問い」「そして新しい関係性」もあります。
小さなきっかけが、未来のお金の土台になることを信じて。



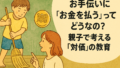
コメント