“お金もらえるバイトあるよ”は危険信号──中高生が狙われる“カンタン副業詐欺”
「スマホで1日30分、即日5,000円!」
「中学生でも月3万円。バレずに稼げる副業あります」
──これ、すべて実際に中高生が見ているSNSやLINEの“副業勧誘メッセージ”です。
今、子どもたちが親の知らない場所で「詐欺のターゲット」になっている現実があります。
「スマホだけで稼げる」は本当に安全?
SNS・LINEで届く“副業詐欺”のリアル
中高生が狙われやすい副業詐欺は、以前のような派手な広告ではありません。
最近では、以下のような形で静かに接近してきます:
- 🔸 友達のフリをしたアカウントからLINEで勧誘
- 🔸 SNSのDMで「実績画像」や「成功者の声」をチラ見せ
- 🔸「登録だけでOK」「即日入金」「バレずに稼げる」がキーワード
表面上は「合法的に見える」「誰でもできる」ように見せてきますが、
ほとんどが詐欺、もしくは詐欺の加害者にされる入口です。
子どもが反応してしまう理由
なぜ、子どもたちはこうした甘い言葉に惹かれてしまうのでしょうか?
- 💸 おこづかいでは足りない欲しいものがある
- 💬 親に言いづらいけど、お金を使いたい場面がある
- 📱 SNS上で“同世代もやってる感”が安心材料になってしまう
「楽して稼ぎたい」というより、「今すぐ欲しい」に共感してしまう──それが落とし穴です。
実際にあったトラブル事例
・「LINE登録だけ」と言われ、個人情報を抜き取られた中2男子
・プリペイドカードの番号を送らされ、家族に損害を与えてしまった中1女子
・「荷物の受け取りバイト」で受け子にされ、犯罪に巻き込まれた高校生
このような事例は、「うちの子には関係ない」と思っていた家庭でも突然起こりうることです。
次はそうした危険から子どもを守るために、親ができる“具体的な声かけと関わり方”を紹介します。
「やめなさい」では届かない。“見抜く力”を育てる方法
副業詐欺に巻き込まれた子どもに、「なんでそんなの信じたの!?」と怒ってしまいそうになります。
でも実は、その反応こそが“報告しづらい空気”をつくってしまう原因にもなります。
大切なのは、「親に相談すれば安心」という信頼関係を普段から育てておくこと。
ここでは、家庭でできる実践的な工夫を紹介します。
① 親子で一度「詐欺DMごっこ」をやってみる
実際に届きそうなメッセージを親が演じて、子どもに「それ信じる?怪しい?」とツッコんでもらうワーク。
たとえば:
- 「このURLから登録すれば、すぐ収益が振り込まれます」
- 「これは誰にも言っちゃダメだけど…」
ゲーム感覚で体験することで、“怪しさの感覚”がリアルに育ちます。
② 「お金をもらう=責任が伴う」ことを具体的に伝える
「ラクに稼げる」だけが一人歩きしている子どもには、“その裏側にある責任”を一緒に考える時間が必要です。
たとえば:
- 🔹 仕事をすると、その内容や報酬は誰かがチェックする
- 🔹 税金、年齢制限、契約のルールも関わってくる
- 🔹 間違えたとき、自分だけで責任を取れるのか?
これを「お金の怖さ」としてではなく、「大人としての信用」という視点で話すと、より伝わりやすくなります。
③ 子どもが知っておきたい詐欺チェックリスト
以下のようなキーワードが出てきたら、警戒サインです:
- 「今すぐ」「今日だけ」「あなただけ」
- 「誰にも言っちゃダメ」「秘密の稼ぎ方」
- 「登録無料」「すぐに振り込み」「LINEだけでOK」
これらは詐欺的な勧誘に共通する“魔法の言葉”。
1つでも当てはまったら、必ず親に報告するルールを決めておきましょう。
次は「副業=悪」ではなく、「働きたい気持ち」をどう育てるかについて、実践的な体験方法をご紹介します。
「働きたい気持ち」は否定しない。“安全な挑戦”に導く
「お金が欲しい」「自分で稼いでみたい」──
こうした気持ちは、決して悪いものではありません。
むしろ、働くことに関心を持ち始めたサインでもあります。
大切なのは、「今はダメ!」と頭ごなしに否定するのではなく、“今の年齢でできる体験”に上手く導くこと。
① 家の中でもできる“疑似バイト”で体験と責任を
「手伝い」や「おこづかい」とは別に、“成果型”の疑似バイト制度をつくってみるのもおすすめです。
たとえば:
- 📦 フリマアプリの出品準備(撮影・梱包・説明文づくり)
- 📋 週次で家の買い出し計画を立て、レシートで検証する“家計アシスタント”
- 🧼 定期的な家事(風呂掃除や料理)をタスク単価制で報酬設定
やった分だけ報酬がある→責任が発生するという感覚を、小さなステップで体験できます。
② 金融・労働リテラシー教材で「働く」の本質を知る
近年では、子ども向けに「お金」「仕事」「投資」などを学べる教材や講座も増えてきました。
実在の企業事例を使った教材や、仮想通貨・ビジネスモデルのシミュレーション体験など、“カンタンに稼げない”現実を学ぶ入口にもなります。
例:
- 🔹 中高生向け「仕事とお金の探究セット」
- 🔹 オンラインで参加できる“バーチャル職業体験”
③ 親子で体験できる“仕事ごっこ”やキャリアイベント
地域のキャリアイベントや、キッズマネースクールのワークショップなどでは、
子どもが「働く」を遊びながら体験できます。
「うまく伝えられない」と感じたら、第三者の視点を借りるのも選択肢です。
働くこと=危険じゃない。
でも、「自分で選び、責任を持つ」経験を積むことが、将来の詐欺リスクから子どもを守る力になります。
大切なのは、禁止ではなく、信頼と機会で育てること──
あなたの家庭にもできる、小さなステップから始めてみませんか?

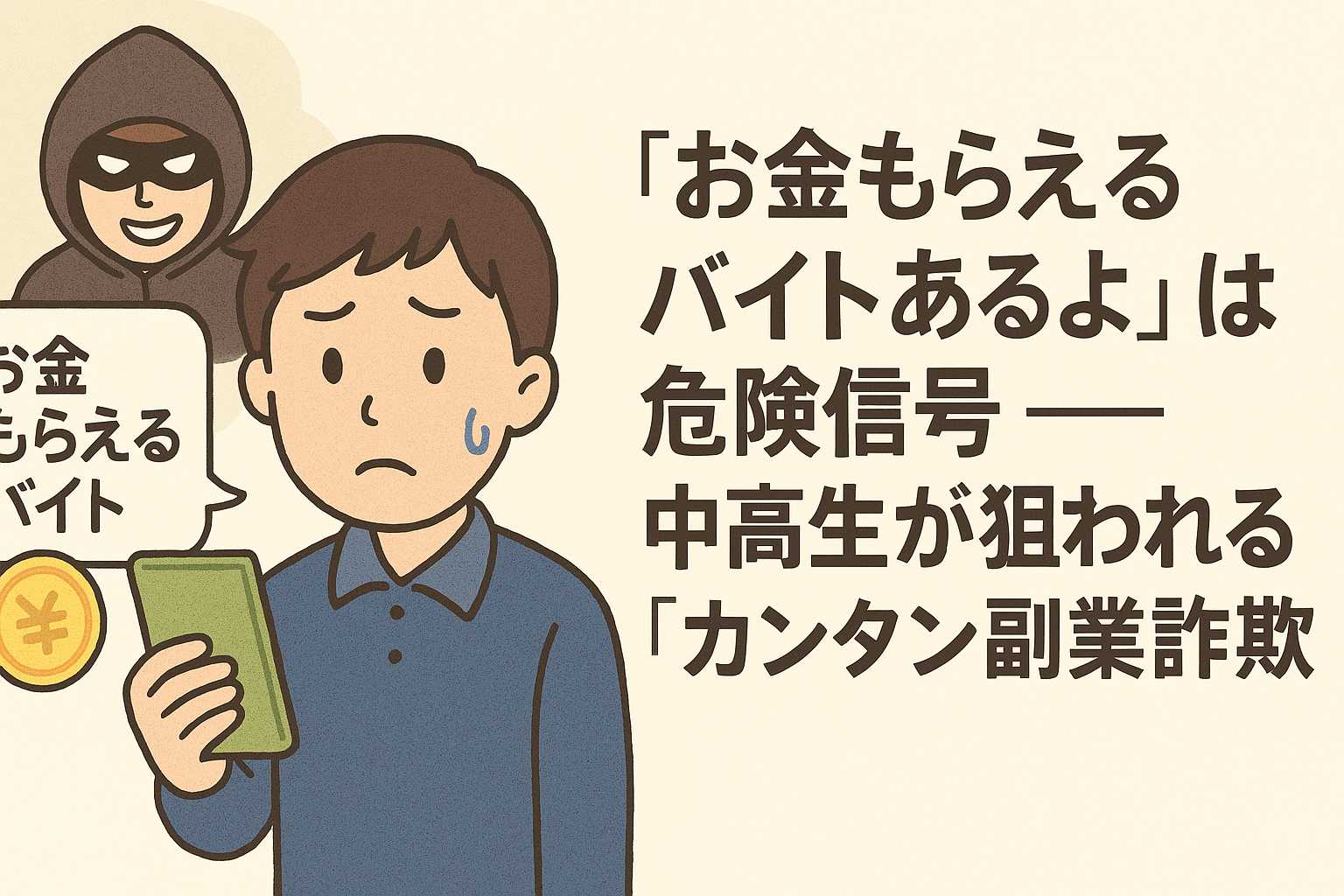


コメント