「海外の水が300円!?」円安・円高って何が違うの?|日本が安く見える理由
「ハワイでおにぎりが500円!?」「海外旅行のたびに“物価高すぎ”って思う…」 そんな声を聞いたことはありませんか? 一方で、「日本は今や“物価の安い国”」なんて言われ、観光地では海外からの旅行者がこぞって買い物する姿も目立っています。 どうして、同じモノの値段が国によってこんなに違うのか? 本当に“物の価値”が違うのか? その鍵を握るのが、通貨のやりとり=「為替」の仕組みです。 この記事では、子どもにもわかるように、「円安・円高ってなに?」を身近な例からひもといていきます。 “お金の価値”は、いつも同じじゃない——そんな視点が、世界の見え方を少し変えてくれるかもしれません。
「日本って、なんでこんなに安いの?」外国人が買いまくるワケ
「100円ショップが最高!」という外国人の声
SNSでは、「日本の100円ショップは天国!」「クオリティが高すぎる!」と絶賛する外国人の投稿がバズっています。 日本に来る観光客の中には、100円ショップでスーツケースいっぱいに買い物する人もいるほど。 たしかに、同じような商品を海外で買おうとすると、2倍、3倍の価格がついていることも珍しくありません。
海外から見ると、日本のモノは“安く見える”?
でも、それって本当に「日本のモノが安いから」なんでしょうか? 実は、海外の人にとって“日本の円が安いから”そう見えている、という側面もあります。 日本の100円は、ドルやユーロに換算するとたったの0.6〜0.7ドル程度(※時期による)。 つまり、海外の人にとっては「60〜70円で買える感覚」なんです。
それって…もしかして「円安」の影響?
この「円が安くなる」ことを、「円安(えんやす)」といいます。 円の価値が下がると、海外から見ると日本の商品は“安く見える”ようになります。 だから、外国人観光客は「日本って安くて最高!」と感じて、買い物を楽しむわけです。 逆に、日本人が海外に行くと、「え、たったこれだけで300円!?」と感じることが増えてきているのです。
円安・円高ってなに?お金の価値が変わるってどういうこと?
同じ100円が、外国でいくらになる?
たとえば、あなたが100円を持ってアメリカに行ったとします。 以前なら100円で1ドル分の買い物ができたのに、今は100円で0.6ドル(約60セント)しか買えない…そんなことが起きています。 これは、日本のお金「円」の価値が、外国のお金「ドル」に対して下がったということ。 こうした「交換レートの変化」が、円安・円高の正体です。
為替は国同士のお金の“交換レート”
「為替(かわせ)」とは、国と国の間でお金をやりとりするときのレート(交換比率)のこと。 これは常に変動していて、ニュースでも「1ドル=○○円」といった形で日々報道されています。 このレートが変わると、海外旅行・輸入品・留学費用など、あらゆる“外国とのやりとり”に影響が出ます。 つまり、為替は「世界とつながるお金のしくみ」そのものなんです。
物価の差は“お金の力”の差でもある
物の値段が高い・安いの背景には、「その国のお金の力(=購買力)」があります。 円の価値が下がれば、外国のものは高く感じるし、逆に円の価値が上がれば、安く感じるようになります。 これは単なる数字の話ではなく、日々の買い物や旅行、企業活動にまで影響する「リアルなお金の感覚」。 子どもにも、「円=世界の中の1つの通貨である」ことを知るきっかけになります。
「安くなる」「高くなる」は、誰にとってどういうこと?
円安は旅行者に有利、日本人には…?
円安になると、日本の商品は外国人にとって“安く”見えるため、観光や買い物がしやすくなります。 そのため、インバウンド(訪日観光)の面ではプラスに働きます。 でもその一方で、日本人が海外に行ったり、外国のモノを買ったりするときには、支払う金額が“高く”なってしまいます。 つまり、円安は「誰にとって有利か」が分かれるしくみなんです。
日本の給料が上がらなければ、輸入品がどんどん高くなる
日本では、多くの食料品や日用品を海外からの輸入に頼っています。 円の価値が下がると、同じモノでもより多くの円を払わなければいけません。 それに対して、日本の給料が上がらなければ…? 生活費ばかりが増えて、実質的に“お金の力”が弱くなってしまいます。
「円安+低賃金」は、国全体にとっては苦しい状態。 だからこそ、物価と同時に賃金が上がる「健全な経済の流れ」をつくることが大切なんです。
「通貨の強さ」は、国の力にも関わっている
円の強さ(円高)や弱さ(円安)は、単なる数字の話ではありません。 それは「その国のお金が、世界でどれだけ信用されているか」というバロメーターでもあるのです。 もちろん、輸出企業にとっては円安が有利な場合もありますが、国民生活にとっては物価上昇や生活コストの上昇がつきまといます。
子どもたちがこれから生きていく社会では、「お金は世界とつながっている」という感覚がますます重要になります。 “円安だから仕方ない”ではなく、「なぜそうなるのか?」「それで誰が得をして、誰が困るのか?」 そんな問いを持てることこそ、マネーリテラシーのはじまりです。

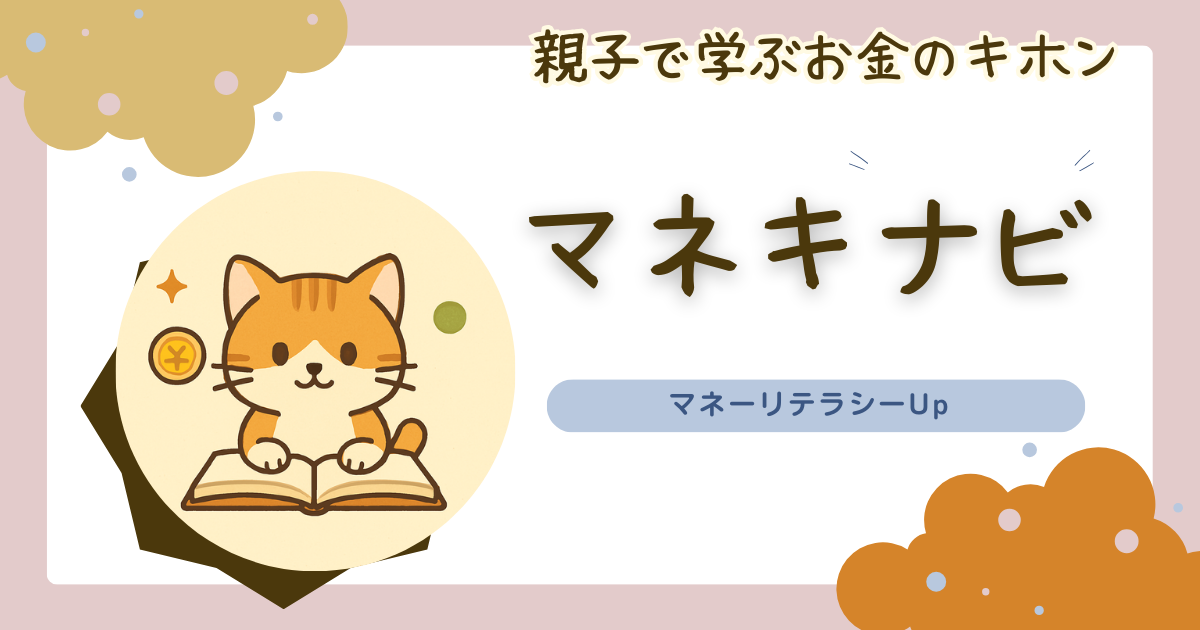


コメント