なんで最近なんでも高いの?|“値上げ”の理由と、その先にある社会のしくみ
最近、スーパーで「あれ?また値上げ?」と思うこと、ありませんか? ジュースやパン、お菓子など、ちょっと前までより10円、20円とじわじわ高くなっている——そんな変化に気づいた子どもから、「なんで?」と聞かれて、うまく答えられなかった…という親御さんも多いかもしれません。 このページでは、子どもと一緒に“値段の変化”をきっかけに、「社会ってどう動いてるの?」「お金の流れって?」をやさしく学んでいきます。 単なる節約や「値上げ=悪いこと」という話ではなく、価格が動くことで見えてくる、世界とのつながりや、私たちの生活のリアルを一緒にひもといてみましょう。
食品がどんどん高くなる…これって誰のせい?
同じジュースが、数ヶ月で10円アップ!?
ある日、いつも買っていた100円のジュースが、110円に。さらに数週間後には120円——。 こんなふうに、気づかないうちに少しずつ値段が上がっている商品がたくさんあります。 子どもも「前と同じお菓子なのに、高くなってる!」と気づくことが増えています。
でも、ここでちょっと立ち止まって考えてみましょう。 「なんで高くなったの?」 「誰かがたくさん儲けようとしてるの?」 本当にそうなんでしょうか?
値上げのニュース、最近多すぎない?
テレビやネットのニュースでも、「食品○○品目が一斉値上げ」などという報道が目立ちます。 けれど、実は企業やお店にとっても値上げは簡単な決断ではありません。 ・「高くしたら、お客さんが来なくなるかも」 ・「値上げしても、従業員の給料にはまわせない…」 そんな板挟みの中で、ぎりぎりの判断をしていることが多いのです。
「企業が儲けすぎてる」って本当?その背景は?
値段が上がると、「企業がもうけを増やそうとしてるんじゃないの?」と思うかもしれません。 けれど実際には、原材料や輸送費、人件費など“かかるお金”が増えていることが大きな理由です。 もちろん一部には過剰な値上げや便乗もありますが、多くの企業は「上げざるを得ない」状況にあります。 ここからは、その“かかるお金”の中身を見ていきましょう。
原材料・円安・人手不足…値段が上がる“ほんとうの理由”
小麦も油も海外から買ってるって知ってた?
私たちが食べているパンやお菓子の多くは、小麦や油などの“原材料”が海外からやってきています。 日本ではこれらの農作物をじゅうぶんに生産できないため、アメリカやカナダ、東南アジアなどから輸入しています。 つまり、海外の作物の出来・値段・輸送コストが、私たちの身近な商品の価格に直接影響するのです。
たとえば、天候不順で収穫量が減れば、当然小麦の価格は上がります。 「日本の農業」だけではなく、「世界の農業」が値段に関わっている。そんな“世界とのつながり”を感じるきっかけにもなります。
円安ってなに?なんで“外国のお金”が関係あるの?
ニュースでよく聞く「円安」。 簡単に言うと、日本のお金(円)の価値が、外国のお金(ドルなど)に対して弱くなることです。 たとえば、以前は1ドル=100円だったのが、今は1ドル=150円になったとします。 そうすると、海外から同じものを買うにも、前より多くのお金(円)が必要になるのです。
輸入が多い日本にとって、円安は「買うコストが増える」ことを意味します。 これは企業の仕入れ価格にも直撃し、結果として商品の値上げにつながっていくのです。
働く人が足りないと、なぜ物の値段が上がるの?
最近は「人手不足」も大きな問題になっています。 運送業や製造業、飲食業など、どの分野でも「働く人」が足りなくなってきています。 人が足りないと、仕事を回すために一人あたりの負担が増えたり、時給を上げたりしなければなりません。 これもまた、商品やサービスの値段に反映されるのです。
人手不足 → 人件費の上昇 → 値段の上昇。 「人が減ると高くなる」というのは、意外と身近でシンプルな仕組みです。
値上げは悪いこと?それとも、よくなるチャンス?
「価格転嫁」が進まないと、苦しむのは誰?
原材料や人件費が上がっても、商品価格にその分を反映できなければ、企業やお店は赤字になってしまいます。 でも、「値上げしたら売れないかも」とためらう企業も少なくありません。 その結果、しわ寄せがくるのは、現場で働く人たち。 給料が上がらず、働いても生活が厳しくなってしまう——そんな“無理”が積み重なると、社会全体が疲れてしまいます。
だからこそ、「適正な価格にする」「上がった分をしっかり回す」という“価格転嫁”は、とても大切な仕組みなのです。
物価と賃金が一緒に上がると、実は社会は元気になる
「物価が上がるのは嫌だ」という声も多いですが、実は物価と賃金が“セットで”上がるなら、それは社会にとって健康的なサインでもあります。 企業が儲かり、人を雇い、給料が増え、みんなが買い物をする。 こうした好循環が生まれると、社会全体が元気になります。
逆に、物価だけが上がって給料が変わらなければ、「実質的に貧しくなる」状態になってしまいます。 大事なのは、「賃金がちゃんと上がること」も一緒に実現していくことです。
「安い=正義」だけじゃない、“適正価格”の考え方
私たちはつい、「できるだけ安く買いたい」と思いがちです。 でも、その裏で誰かが無理をしていたり、我慢していたりすることもあるかもしれません。 だからこそ、「安ければいい」という考えから、「その値段で、みんながちゃんと報われてる?」という視点に変えていくことが、これからの時代に求められているのです。
子どもと一緒に、値段の“意味”や“背景”を考えることで、モノを見る目や社会への視点が深まります。 「なんでも高くなったね」で終わらせず、「それってどうして?」と問い続ける力が、未来のマネーリテラシーにつながっていきます。


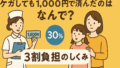

コメント