子どもが“詐欺”に遭う前に──小学生から教えたい3つの“お金の罠”
「そんなの引っかかるわけないでしょ」
そう思っていたのは、大人の感覚でした。
でも、現実にはスマホやSNS、ゲームなどを通じて小学生が“お金のトラブル”に巻き込まれるケースが確実に増えています。
ポイント詐欺、無料アイテム詐欺、簡単に稼げる系の勧誘…。
それらは子どもにとって“善悪の判断がつきにくいグレーゾーン”として迫ってきます。
この記事では、子どもに今すぐ伝えておきたい「3つの金銭トラブルの罠」を、具体例を交えて解説します。
被害に遭う前に、「気づける子」になるための家庭での声かけも紹介します。
子どもが“まさか”の被害者に?増える金銭トラブルの実情
なぜ今、詐欺のターゲットが子どもにまで広がっているのか
従来、詐欺や金銭トラブルの対象は「高齢者」が多いとされてきました。
しかし近年、スマホを使う小学生〜高校生にも“お金の甘い話”が届く時代になっています。
SNSのDM、ゲームアプリ内のチャット、LINEスタンプをエサにした誘導リンク…。
デジタルの中には、子どもの判断力を狙ったトラップが潜んでいます。
「うちは大丈夫」が通じない時代の親の責任
「子どもにそんな危ないことさせてないから」
「ちゃんと注意してるし、管理してるから大丈夫」
──そう思っていても、子どもは大人が思わぬところで“情報”と“選択”に触れています。
重要なのは“制限”だけでなく、“自分で判断できる力”を育てること。
その第一歩として、どんな手口があるのかを一緒に知っておくことが大切です。
実際にあった子ども向け詐欺・勧誘トラブルの事例
- 🔹 ゲームアプリで「課金アイテム無料ゲット」リンクを踏み、情報漏洩
- 🔹 SNSで「あなたの絵を買いたい」と言われ、口座情報を送信してしまう
- 🔹 小学生向け動画に「これで1万円稼げた!」というポイント商法が紛れ込む
次はこうした被害につながる「3つの典型的な罠」を解説します。
小学生にも伝えられる言葉と視点で、親子で確認してみましょう。
小学生でも理解できる、“お金の罠”の基本パターン
子どもが巻き込まれやすい金銭トラブルには、いくつか共通した“型”があります。
ここでは、特に多い3つのパターンを、小学生にも伝わるような言葉で解説していきます。
① 「無料」の罠──タダより高いものはない
「無料で〇〇がもらえる!」
「送料だけで、豪華アイテムが手に入るよ!」
こうした言葉に惹かれて、個人情報や決済情報を入力してしまうケースが後を絶ちません。
大切なのは、「本当にタダなのか?」を考える力。
住所・電話番号・メールアドレスなどの入力を求められる場合、それ自体が“支払い”になっていることも。
また、「無料の代わりに広告を見せられる」ことで、子どもが詐欺系ページに誘導されるリスクもあります。
② 「楽に稼げる」罠──簡単に稼げる話ほど怪しい
「ゲームをプレイするだけでポイントが貯まる!」
「スマホだけで1日3000円のお小遣いが!」
こんなうたい文句が、子ども向け動画やSNSで当たり前のように流れています。
ですが、実際にはクリック誘導のための広告だったり、不正アプリへの誘導であることも多く、最悪の場合、保護者のスマホやクレジットカードに被害が及びます。
「楽に稼げる」は、ほぼ間違いなく“ウソ”または“裏がある”という感覚を、小学生のうちから持っておくことが大切です。
③ 「誰にも言っちゃダメ」の罠──秘密の取引には裏がある
「これは誰にも言わないでね」
「親に見せないでって約束してね」
──この言葉が出てきたら、その先には“危険”しかありません。
詐欺や不正行為の多くは、「親にバレなければOK」という心理を逆手に取ります。
秘密のやりとり・DM・画像共有など、子どもが孤立した状態で動いてしまうと、被害が拡大しやすくなります。
「内緒にして」が出てきたら、すぐに親に相談するというルールを、ぜひ家庭で共有しておきましょう。
次はこうしたトラブルを防ぐために、家庭でできる対話や教材・ワークショップなどの活用法をご紹介します。
騙される前に、“話しやすい家庭”と“考える習慣”を
詐欺に遭わないために、最も効果的な方法は「知識」だけではありません。
それは、「これってヘンかも…」と感じたときに、すぐ誰かに話せること。
そして、日常の中で“考える力”を育てることです。
詐欺は知識よりも「相談できる環境」で防ぐ
加害者の多くは、「親に言えない」状況を作ろうとします。
だからこそ、家庭で「どんなことでも話していいよ」と伝えておくことが、最大の防御策になります。
子どもが「こんなこと聞いたけど変じゃない?」と自然に話せる空気づくりを、ぜひ心がけてみてください。
「これって変じゃない?」を言える雰囲気づくり
- ✔️ ニュースやCMを見ながら「これってどう思う?」と問いかけてみる
- ✔️ 子どもがスマホを触っていたら、気軽に「何見てるの?」と聞いてみる
- ✔️ “詐欺を防ぐ”より“話せる関係”を育てる姿勢を持つ
詐欺対策は、ルールよりも関係性がカギになることが多いのです。
家庭でできる対話ワーク・おすすめ教材・体験イベント
もしもう一歩進めたいなら、以下のような体験型の取り組みも効果的です:
- 🔸 詐欺体験ワーク(家庭用台本つき):親子で詐欺師役・相談者役を演じてみる
- 🔸 マネー&防犯ワークショップ:全国で開催される体験講座(オンラインもあり)
- 🔸 子ども向けマネー教材キット:詐欺・情報リスクを学べる紙&デジタル教材
難しい言葉ではなく、“やってみる”体験から「気づく」ことが、子どもの心に残ります。
将来的な自衛力へ──“本物のお金”に触れる次のステップ
「うそを見抜く力」は、「本物を知る力」でもあります。
たとえば、おこづかいや家庭内の予算の中で「どう使うか」「何に価値を感じるか」を一緒に話すことも、“お金の現実”に触れる第一歩です。
親が使っている投資や預金のことを具体的に見せる必要はありませんが、「なぜこの買い物を選んだのか」「何のために貯めているのか」といった話題を通じて、“お金を育てる感覚”を自然に伝えることができます。
小さなことでも構いません。
まずは、今日から「うちの子と、1つお金の話をしてみよう」から始めてみませんか?

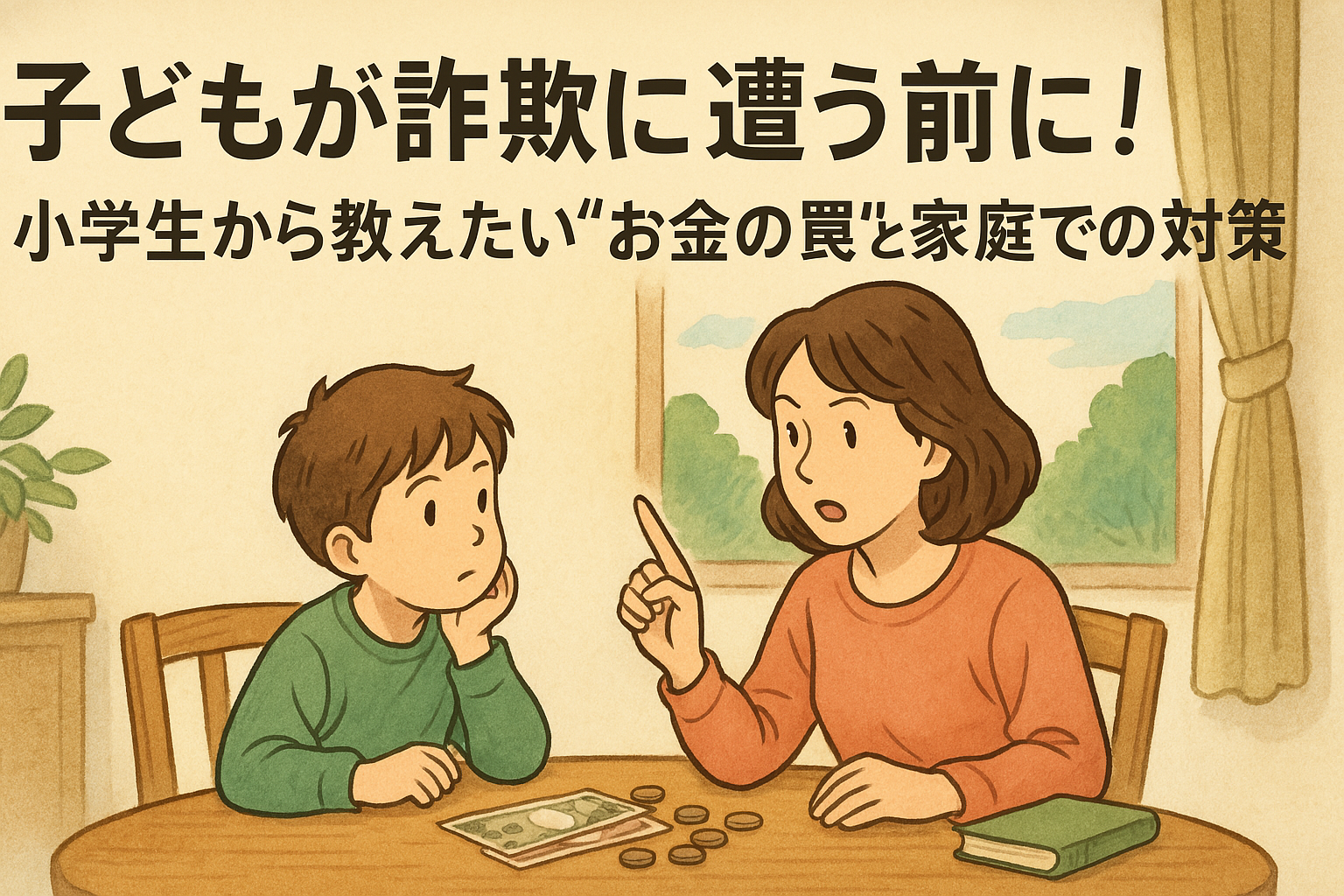

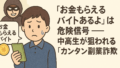
コメント