現金と電子マネー、どっちもある今だからこそ学べること
場面によって「使いやすさ」が違うのを体感できる
現金と電子マネー、どちらも便利だけれど、「いつ、どちらを使うとスムーズか」を判断するには、実際に使ってみるのがいちばんです。
駄菓子屋で育つ「計算する感覚」
たとえば駄菓子屋。10円、20円と細かく買う場所では、現金が圧倒的に便利です。「120円あって、これとこれを買ったら…」と計算しながら選ぶ経験は、子どもにとって“お金の感覚”を養う絶好のチャンスになります。
電子マネーは「おつりのわずらわしさ」を減らしてくれる
逆に、コンビニや自販機などでは、電子マネーが本領発揮。130円の買い物に1000円を出しておつりを受け取って…という手間がなく、「ピッ」で済む手軽さは、子どもにとっても気軽に使える良さがあります。小銭が増えないのは、親にとってもありがたいところ。
“使えるかどうか”を確認する経験も、判断力につながる
「このお店、電子マネー使えるかな?」と気にするのって、大人なら無意識でも、子どもにとっては新しい気づきです。出かける前に調べるほどではなくても、レジに並ぶ前にマークを探す、聞いてみる——それもひとつの“判断”の練習になります。
この「現金の方がいいとき」「電子マネーが便利な場面」を体感することが、使い分けのセンスを育ててくれます。どちらかに決めるのではなく、その都度選ぶという感覚こそが、お金の使い方の土台になっていくのです。
管理の仕方が違うから、感覚も変わってくる
現金は「財布を開いたらすぐ残高が見える」「お札が減ると焦る」など、感覚的な実感が強いのが特徴。反対に電子マネーは「残高はアプリで確認」「うっかり使いすぎても気づかない」という面もあります。
たとえば、「買った覚えがないのに残高が少ない」と言う子が、あとから履歴を見て「あっ、そういえば…」と気づくケースはよくあります。
この違いを経験すると、「どっちの方が自分に合ってる?」「どうやったら管理しやすい?」という視点が自然と生まれてきます。これは大人でも意識しないと育たない感覚です。
選ぶ経験が“自分で考える力”を育てる
「今日はPayPayで払ってみよう」「これは現金の方が早そう」——そんなちょっとした選択でも、「自分で判断した」という感覚は大切な成功体験になります。
たとえそれが「間違った判断」だったとしても構いません。「電子マネーしか持ってこなくて買えなかった」なんて経験も、次回からの行動を確実に変えていきます。
親としては、結果に口出しするよりも、「なんでそうしたの?」と対話のきっかけにしてあげることで、金銭感覚はぐっと育ちやすくなります。
わが家流“使い分けノート”のすすめ
「なぜこっちを使った?」を書くだけで学びになる
「何に使ったか」ではなく、「なぜその手段を選んだか」。この“選んだ理由”に目を向けるだけで、金銭感覚の育ち方は大きく変わります。
たとえば、「PayPayで払ったけど、よく見たら現金なら5円引きだった」とか、「Suicaしか持ってなくて、買えなかった」など——使い分けの結果に“理由”を添えるだけで、そこに気づきが生まれます。
これは親が「なぜ?」と問い詰めるのではなく、あくまで子どもが“自分で気づけるようにする”ための工夫。使い分けノートは、その気づきの貯金箱のような存在です。
書き方はシンプルでいい
「いつ・どこで・どう払ったか」「なぜそうしたか」——この2点だけを軽くメモするだけでOK。日記のように書いてもいいし、LINEにぽつりと送ってもいい。習慣化が目的なので、手段は自由で大丈夫です。
できれば最初は、親も一緒に「今日はこれに1000円使っちゃったんだけど、ほんとはいらなかったかも」など、自分の気づきを共有してみると、子どもにとっての“モデル”になります。
「書かせる」ではなく、「一緒にふりかえる」くらいのスタンスで続けていけると理想的です。
ノートが“ふりかえり習慣”になれば、形は自由でいい
「現金派・電子マネー派」よりも大切なこと
おこづかいを現金で渡すか、電子マネーで送るか。それ自体は、実はどちらでも構いません。大事なのは、「どちらを選ぶか」を子ども自身が考え、納得して使っているかどうかです。
「自販機は現金の方が早い」「履歴を残したいからPayPayにした」——そんな理由でも十分。選んで使う経験を積むことで、お金の使い方に責任が生まれます。
つまり、“どう渡すか”ではなく、“どう育てるか”が家庭ごとにデザインできる時代になったということです。
家庭ルールはアップデートしていこう
はじめから完璧なルールを作る必要はありません。「やってみたら、ちょっと不便だった」「こうした方がうまくいくかも」という試行錯誤を重ねながら、家庭のルールもアップデートしていくのが理想です。
大事なのは、「親が決めたルール」ではなく、「親子でつくったルール」。子どもにとっても、自分が関わったルールの方が納得感があり、守ろうという気持ちが芽生えやすくなります。
ふりかえりノートは、その対話の土台。書くことが目的ではなく、「ちゃんと考えてるね」と言ってあげられる時間をつくるための道具です。
お金の使い方は“選び方”から育つ
電子マネーと現金、どちらが正しいかを決める必要はありません。今は「どちらもある」時代。だからこそ、その違いを感じ、どう使い分けるかを考える経験が、子どもにとっての大きな学びになります。
使い分けノートは、その学びを“見える形”にするための道具。完璧に記録する必要はなく、「なんでこっちを選んだんだろう?」と考える時間が、金銭感覚の土台をつくります。
大事なのは、正解を教えることではなく、「気づけたこと」を喜び合える関係でいること。「間違えちゃったけど、自分で気づけた」が、子どもにとって一番の成功体験になるかもしれません。
“ふりかえり”の習慣は、将来、もっと大きなお金を使うときにも必ず役立ちます。おこづかいのうちから、「どう使うか」を考える経験、はじめてみませんか?

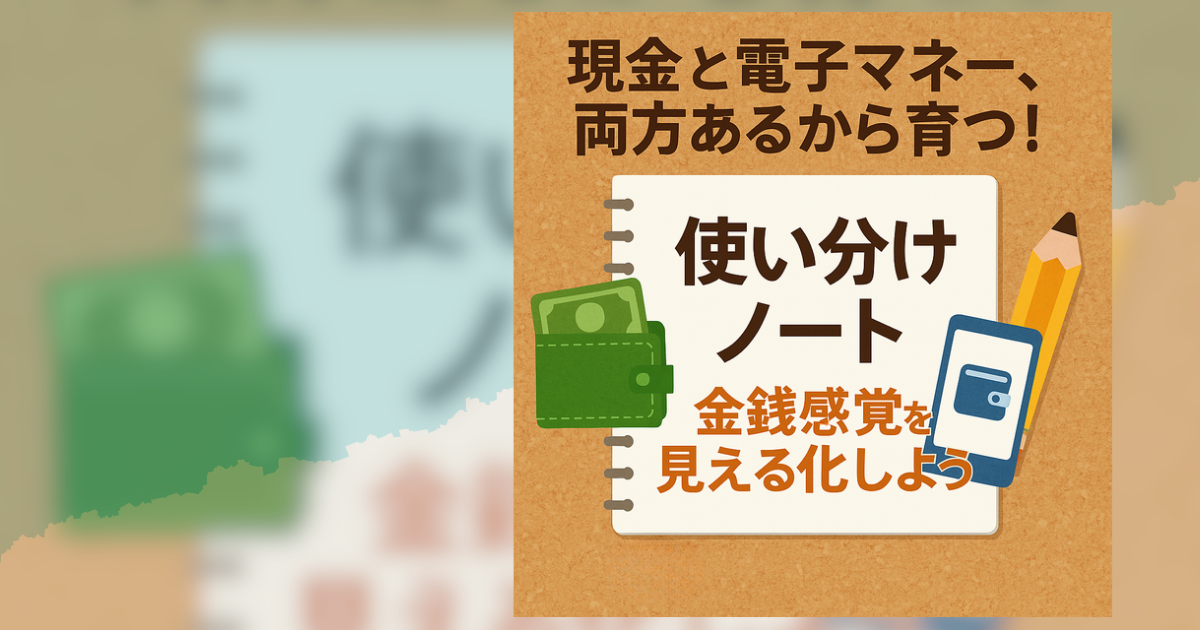
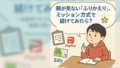
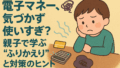
コメント